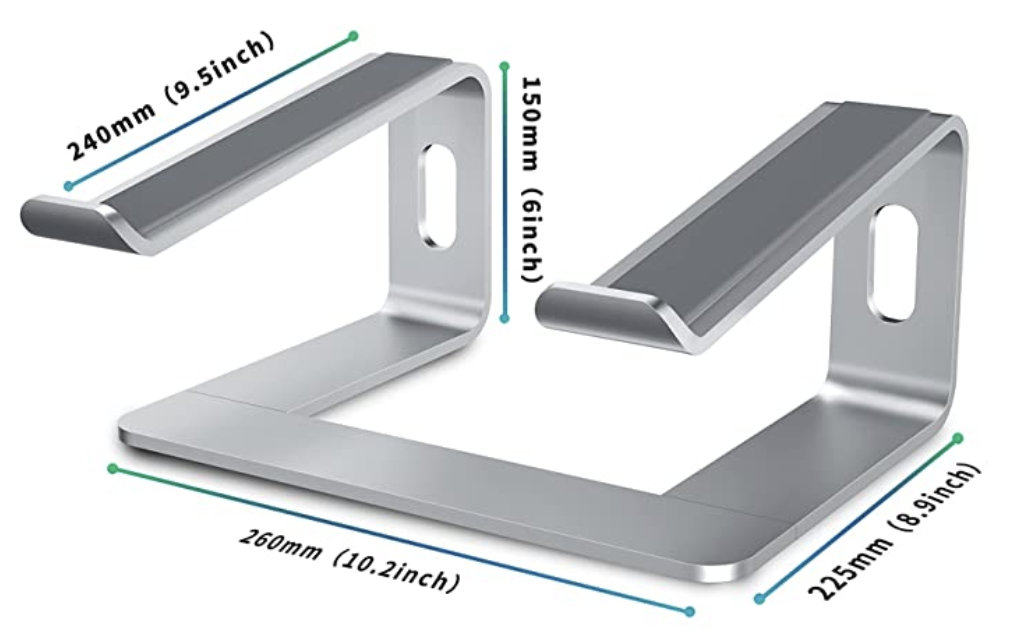クリアしました。プレイ時間70時間ぐらい。
なんというか、たいへんにすごくて、あまり類のないタイプのゲームであり、いやまあすごかったなと思った。がなんというか、ゲームの要素がどれもこれも自分にはいまひとつフィットしなくて、うーんこれは自分向きではないな……という違和感というかなんというか、そういうものをずっと思ってたゲームでもあった。そういう気持ちはエンディングまで解消されなかったかな。
たとえばなんだけど、ウルトラハンドによっていろんなものを構築できる能力。ネットのいろんな記事なりなんなりを眺めていると、とにかくみんなこの能力をつかっていろんなものを作って楽しんでいるようだ。が、自分はいっさいそういうことをする気になれなかった。ゲーム内の障害を解決するために、パズルを解くためにいろいろ考えるのは好きだしやるけど、そうでもないところで何かをやってみようという気持ちがいっさい湧かない。馬車的なものも(大妖精クエスト以外では)一度もつくらなかったし、ほとんどの移動は徒歩とワープだけでこなした。そういうものに興味が出てこないんだよね。マインクラフトに興味がわかないのと同じだな。
スクラビルドも同様で、ああこれは無限に強化アイテムが湧いてくるから適当な武器を強化して消費していくゲームなんだな、ということはまあわかる。わかるんだけど、はっきりいってめんどくさいなと思う。ここに面白さを感じることはついぞなかった。あとどうでもいい話なんだけど、主人公は特殊能力で武器にいろいろくっつけられるという設定なのに、そのへんの雑魚的もいろいろも武器にくっつけられるのはどうなってるんだ。
戦闘のアクション。今回はいつものゼルダよりも前作ブレス・オブ・ザ・ワイルドよりもだいぶ戦闘のアクション要素が高まっているように感じた。作ってるほうとしては折角いろんな戦闘用の動作や要素を盛り込んだのにそんなに活用されないのはもったいないといった面があるのかもしれないけど、正直こういうのあんまり得意じゃないというのもあるし、かったるいし、たいへん。とくに終盤の展開というかラストバトル周辺はほんとうにうんざりした。そして自分はゼルダにそういうことを求めていないという気持ちが高まった。
メインクエストや祠などのパズルっぽいタスクは楽しめるし、ウオトリー村の復興タスクとかはけっこう楽しい(海賊退治はめんどくさくてイヤイヤこなした)。メインクエストのボス戦もしんどい奴はいるけどそんなに嫌いじゃない。つまり自分はパズル的な要素とかギミックとかをゼルダに求めているのだな、という気がする。本作は、全体的にパズルっぽさはずいぶん抑えられていたように思う。それよりは戦闘と、工作による創意工夫が強調されていたかんじ。そのへんがnot for meなかんじだったな。あと前作もそうだったけど祠をさがすのがかったるすぎる。コログの運搬もすぐ飽きてスルーしてた。全般的にやりこみ要素に興味がないのだよね。でもBotW以降のゼルダというのはやりこみ要素だけで構成されてるようなゲームなんだよな。
ストーリー。まぁゼルダというのはストーリーはあってなきがごとしというか、メインのゲーム要素に対する刺身のツマ的な意味しかないと思うけど、でもなんかいまいちだなーと思った。全般的なバックストーリーがそのまんま天孫降臨でキーアイテムが勾玉のかたちなのも、わざとな含意じゃないだろうけどちょっとたじろいてしまったし、賢者の能力がクライマックスの展開にいまいち絡んでこないのも今ひとつ白ける。賢者として覚醒したから魔王を倒せた、みたいなストーリーになっていない気がする。サブクエストのストーリーもそこまで興味がわかないし、サブクエストの報酬が全体的にしょっぱくてやるモチベーションが薄かった。すごいアイテムをもらってもすぐ壊れるか消費しちゃうかだし、経験値とか成長要素は基本的にはないし……。
まぁいろいろ書いたわりには70時間以上プレイしているわけだし、全体的には面白いゲームなんですよ。でもやはり、not for meなところが強かったですね、という気持ち。今後のゼルダは基本的にこういう構成になるみたいだし、もう続編やりたくないかもなあとすら思ったかな。